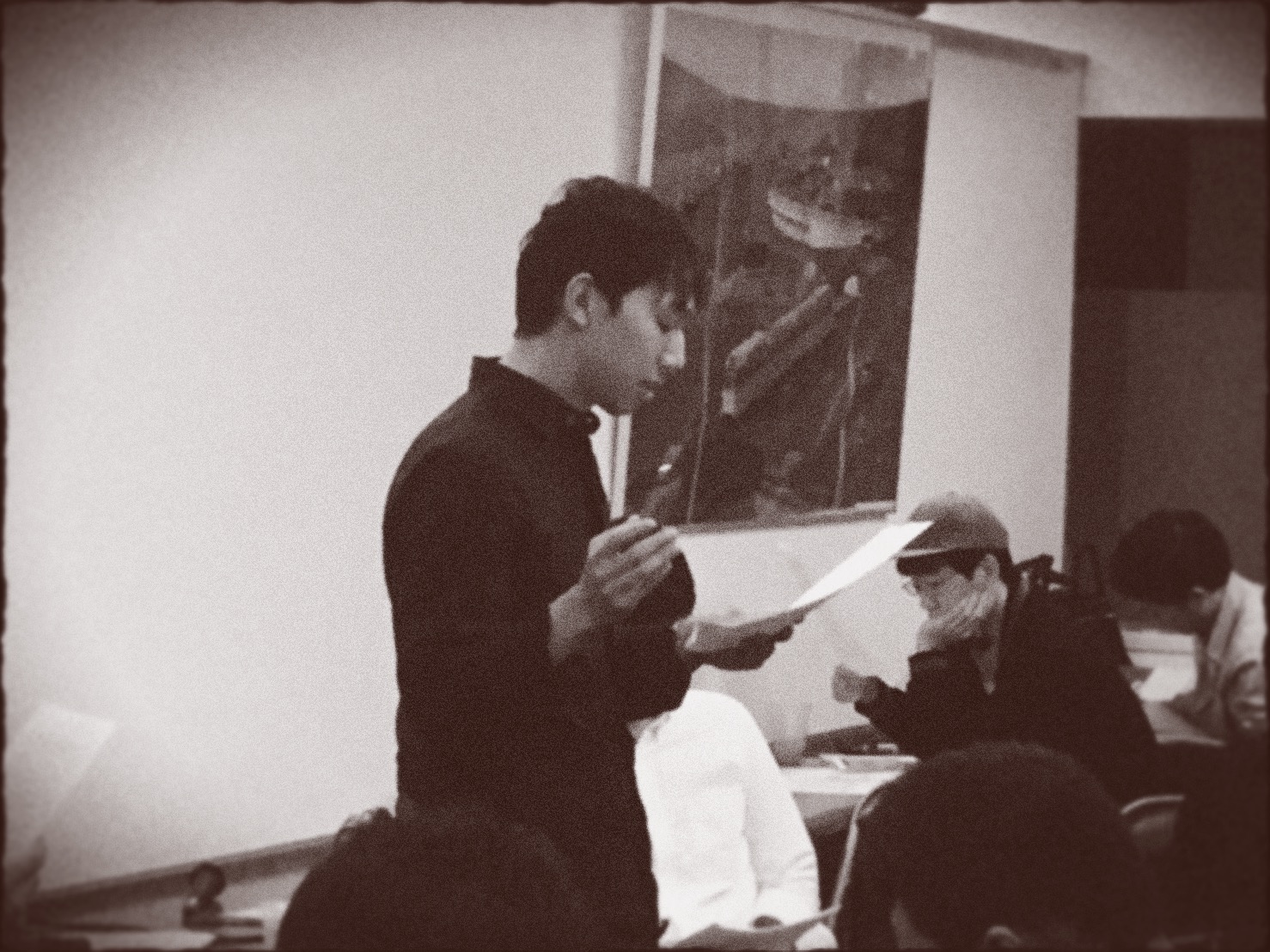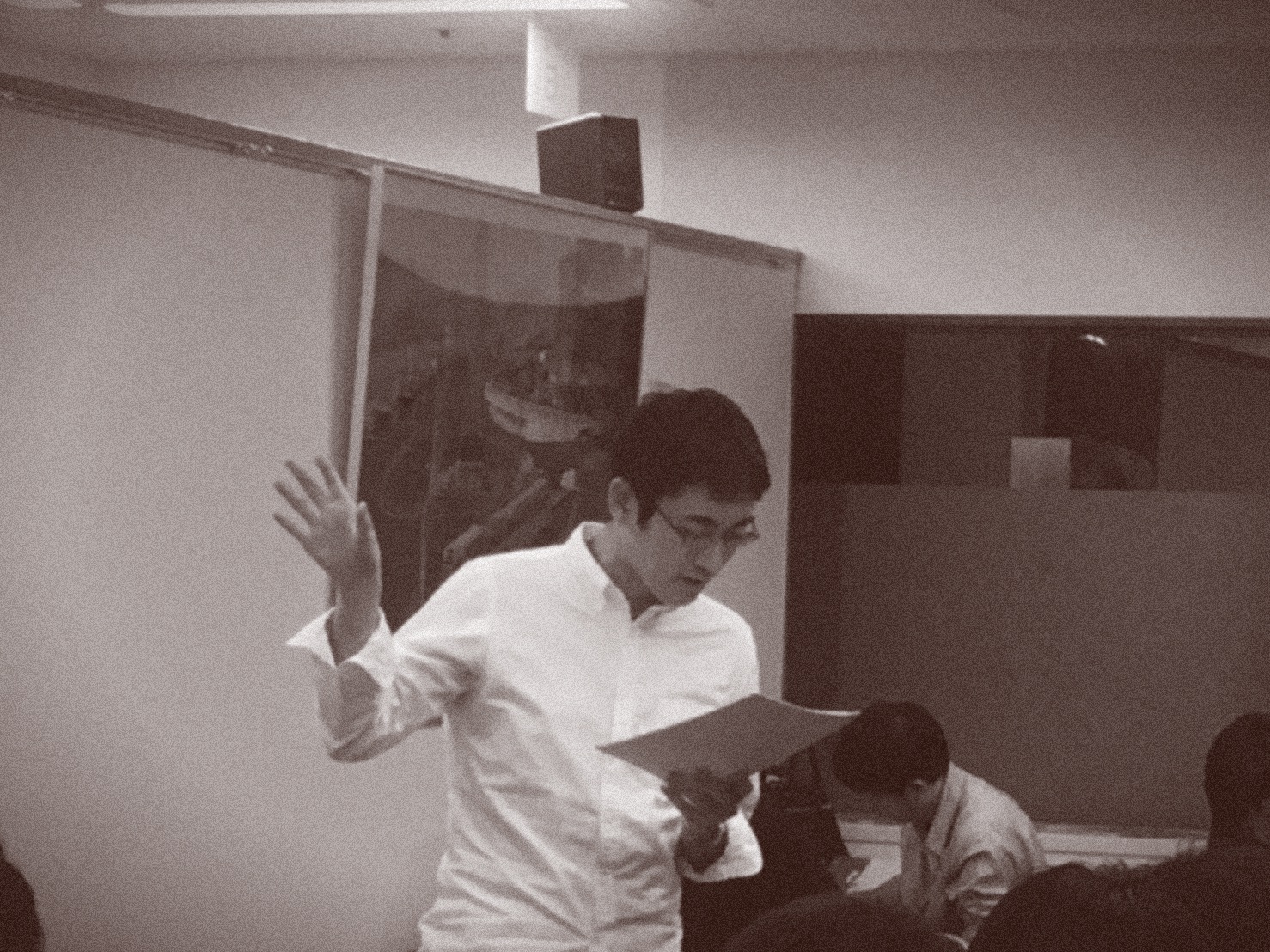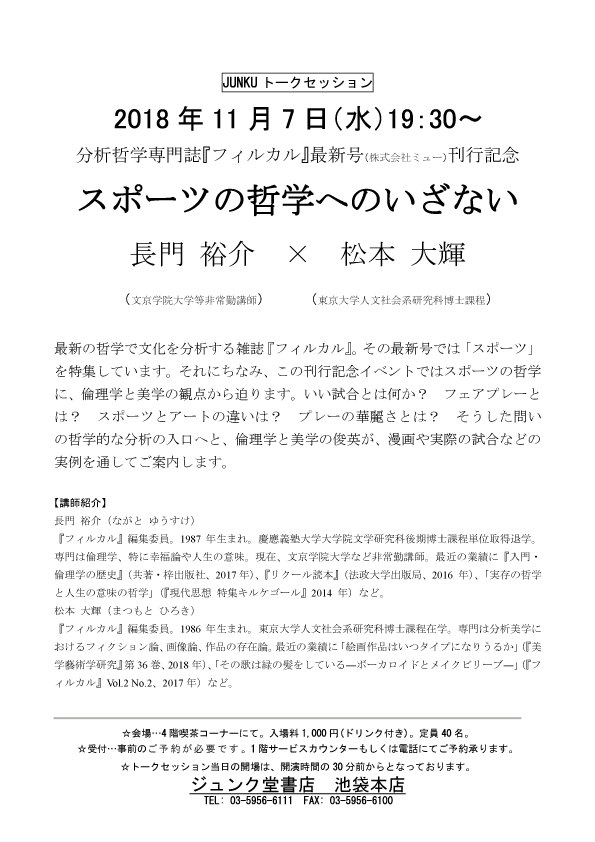2018年9月30日刊行の『フィルカル』Vol. 3, No. 2には、トークイベント記事が掲載されています(262-291頁)。これはそのひとつ前の号『フィルカル』Vol. 3, No. 1の刊行を記念して2018年4月21日にReadin’ Writin’で行われたイベントの記録ですが、紙幅の関係上、発表者による発表部分だけが掲載され、ディスカッション部分を収めることができませんでした。ここではそれを補うため、ディスカッション部分を掲載します。(当日の様子はこちらの記事でも簡単にご紹介しております。)
あらためてイベントの内容を簡単に紹介しておきますと、メインスピーカーとして『フィルカル』Vol. 3, No. 1に論文の掲載された高田敦史氏と岩切啓人氏、司会・コメンテーターとして弊誌編集委員の森功次氏を迎えて行われました。高田氏と岩切氏にそれぞれの論文、「スーパーヒーローの概念史―虚構種の歴史的存在論―」(Vol. 3, No. 1, 170–222頁)および「創造と複製―芸術作品の個別化―」(同128–169頁)の内容やモチベーションを一般向けにわかりやすく伝えてもらったうえで、参加者との間でディスカッションを行いました。両氏の発表内容はVol. 3, No. 2でご確認いただけます。そちらをお読みになったうえで、ここにまとめたディスカッションをお読みいただけたらと思います。なお、当日のディスカッションでは、高田氏と岩切氏に対して順序関係なく質問がありましたが、ここではそれぞれに対する質疑応答をまとめて掲載します。また、ページ参照のある箇所は弊誌Vol. 3, No. 2からのものです。
ディスカッションの最後は思いがけず「ネタバレ問題」へと到達して、盛り上がりを見せています。なお、「ネタバレ問題」については、現代美学研究会主催、弊誌共催で新たなイベントが開催される予定です。 2018年11月23日(金) 大妻女子大学 千代田キャンパス 本館F棟632にて、登壇者は森功次、松永伸司、高田敦史、渡辺一暁の各氏、コメンテーターには稲岡大志氏を迎えます。ここでの議論はその「予習編」になっているとも言えますので、ぜひご確認のうえ、イベントをお待ちいただけたらと思います。
1 高田氏への質問と応答
「スーパーヒーロー」という概念の規定
参加者A
「スーパーヒーロー」という言葉の文献上の初出はあるんですか。
高田
それはけっこう微妙です。『スーパーマン』以前の用例は確認されていますが、現在とは違う意味で使っていると言われます。『スーパーマン』に影響を受けたキャラクターという意味での「スーパーヒーロー」の初出がどこかはわかりません。私が調べた限りでは、41年にすでにそういう用法がある。41年にコミックの描き方ハウツー本みたいなのに「スーパーヒーローを描きたいなら」みたいなフレーズが出てきている。
参加者A
では発表の中で38年とした根拠は。
高田
38年は作品『スーパーマン』が生まれた年で、そこに「スーパーヒーロー」という用語は出てこないんですが、今の「スーパーヒーロー」の用語は〈『スーパーマン』に影響を受けたキャラクターたち〉という意味で使われているからです。
森
38年に生まれたのは「スーパーヒーロー」という言葉で指せる対象ということですね。
参加者A
言葉自体が確認できているのが41年だと。
統語論的には「スーパーヒーロー」は「ヒーロー」に「スーパー」という形容がかかっていると解釈しますが、「ヒーロー」自体はギリシャ起源で、その後もずっと使われている。「スーパー」は超越性みたいな意味があるかと思います。「ヒーロー」と「スーパーヒーロー」の違いは何でしょうか。
高田
スーパーヒーローの定義に関しては〔試みが〕いろいろあるんですが、僕は定義できないのではないかと思っています。コミックブックというメディア自体は34年にできていて、そこからスーパーマンが出てくるまで4年しか経っていない。当時のスーパーヒーロー概念は、あえて言えば「スーパーマンに影響を受けた、コミックブックというメディアにおけるキャラクター」みたいなものです。「ヒーロー」という抽象的な内容にこれを足したら「スーパーヒーロー」になるといったものではなく、〔スーパーヒーローという概念は〕個別的なメディアに結びついたかなり特殊なものだということです。
参加者B
「スーパーヒーロー」という言葉の「スーパー」という部分は「スーパーマン」からきたということでいいんですか。
高田
そうではないです。「スーパーヒーロー」で固有名詞化している。英語では「super hero」という二単語ではなく「superhero」という一単語になっています。
参加者A
「スーパーヒーロー」が日本に輸入された時点というのがあると思います。日本の側でも〔その後発展したものを?〕そのまま「スーパーヒーロー」と呼べるのか、「正義の味方」のような違うものに近いのか、どちらなのでしょう。
高田
「スーパーヒーロー」の定義をやっている人たちはいて、それは論文の中で紹介しているんですが、私はそういう抽象的な定義が立てられるとは思っていないんですね。
〔スーパーヒーローには〕いろいろな特徴があって、日本のものも基本的な特徴は似てはいる。人間以上の力をもっているとか、コードネームをもっているとか、特別な衣装を着ているとか。でも違いもあります。日本のスーパーヒーローは変身するがアメコミのほうはそうではないというようなことです。ジャンル自体が日本とアメリカで二分していて、同じ「スーパーヒーロー」の語で呼ばれていても、本当に同じものなのかどうかはわからない。
この論文ではスーパーヒーローの概念を一切定義しようとせず、なぜ人々は一群のキャラクターを同じスーパーヒーローという名前で分類するのかを追うことに専念しています。
アメコミの場合はなぜスーパーヒーローが虚構内的概念になったのか
参加者C
スーパーヒーローという概念が虚構内でも使われるようになるというのは面白くて、他に探そうと思ったのですが、なかなか見つからない。たとえば日本の特撮のスーパーヒーローの場合もいろいろなヒーローがみんな集まって、という回はあるが、自己言及的なものにはなっていない。日本の場合は子供向けだから複雑なことをやらない、という事情もあるかもしれないですが、アメリカの場合にそれが成り立った事情はあるのでしょうか。
高田
なぜ定着したかは僕もわからない。日本の場合でも単発では同じようなことがあって、オールスター映画などでは、仮面ライダーやプリキュアが集まって、「俺たち仮面ライダーだから」とか「私たちプリキュアだから」みたいなことを、普段の作品では「仮面ライダー」という言葉を使わないくせに、突然言い出すわけです。アメコミの場合はそれが常態化していて、それはユニバース制度のようなものができたからだと思います。
だんだん時が経ってくるとジャンルの中にジャンルが繰り込まれるという現象自体はいろんなものにあって、ホラー映画でもメタ・ホラーのようなものが出てきて、ホラー映画の登場人物がみんなホラー映画を見ていてホラー映画に詳しくて、ホラー映画のジンクス(夜中プールに行くとやばい、とか)を言い始めて、というのはあるけれど、それが当たり前の状態になっているのは珍しくて、それはユニバースのようなものができたせいなのではないかと思っています。
参加者C
ユニバースは独特ですよね。いろんな作品が全部いっしょになったら、という発想自体はいろんな人が抱きがちだけど、そういうものは普通定着しないですよね。
高田
実際作るのはたぶん難しいと思います。映画でも結局マーベルぐらいしかうまくいっていない、という話もありますね。DCはうまくいっていないし、ダークユニバースというユニバーサルのモンスター映画のやつがあったんですが、それも1作目でこけた。そんなに簡単にいくものではないのではないか、と思います。
参加者C
逆に言うとなんでマーベルはそんなにうまくいったのでしょう。
高田
スーパーヒーロー像が変わった、みたいなのと本当はリンクしていて、ただ作品をつなげればよいという話ではなくて、ジャンル全体に対するメタな楽しみ方をセットにしないとうまく回らないというのが本当はあるんじゃないかな、と思います。
虚構内的概念の使用を描くことにはいまだメタ的・パロディー的な意味があるのか
参加者B
ルーク・ケイジの例〔274頁、図2〕では先ほど笑いが起きて、笑えるんですが、笑いを意図したものとして出しているのでしょうか。
高田
パロディーとしての視点はたぶんあると思うんですけど、1970年代ぐらいからこれがむしろ当たり前のことになっています。自分で衣装を作るシーンはだいたいあります。
参加者B
メタレベルのときはある種のパロディーというか、標準からのずらしでやっている感じだと思うんですが、常態化するともうメタではなくなっていて、ジャンルの中に組み込まれている、という感じでよいのでしょうか。それともまだメタ的なものとしてそういう表現があるのでしょうか。
高田
それは難しいですね。メタ的な面白さもある気がするんだけど、表現としては一般化しているという感じがあるのかな。
森
最近の作品の物語世界の中では「変な格好をしている」という含意はあるんですか。
高田
昔は衣装について何も言わないけれど、最近の作品では、むしろそうしたメタな発言がわざとでてきて、それがかっこいいという感じがありますね。
岩切
こういうのは作品外で作者が読者に語りかけている(完全にメタである)のではなくて、完全に作品内に落とし込まれているということでよいのでしょうか。
高田
持ち込まれているとは思うのですが。
参加者B
メタフィクションっていうのは本来作者と読者の関係であるものが、キャラクター内部の者が言っている、ということで、そうであるのは確かなんじゃないですか。それがどういうふうに機能するか〔が問題ではありますが〕。
高田
読者に対する目配せはあるだろうとは思います。
作品内の人々はスーパーヒーローをフィクションとして知ることがあるか
森
最初にフラッシュが2人出てくる作品(「二つの世界のフラッシュ」)があるじゃないですか。1人のフラッシュが先代のフラッシュがいる世界に行って、コスチュームのまま行くんだけど、そこでホットドッグかハンバーガーか何か売っている店員に「お前はなんでそんな変な格好してるんだ」と言われる。あの世界の人たちの間には「スーパーヒーローというのは変な格好している奴だ」という共通認識がもしかしたらないんじゃないか。
高田
ないと思います。それはやっぱり時代的にユニバース形成前なので、スーパーヒーローがいるのが当たり前って世界にはなっていない。60年代のマーベルだとスーパーヒーローが出てきたときにそのへんの普通の人が「また新しいスーパーヒーローか」みたいなことを言ったりする。
森
我々現実世界の人たちがもっているスーパーヒーロー概念からしたら、スーパーヒーローというのはあくまで作り物、フィクションなんだけど、中〔虚構世界内〕の人たちのスーパーヒーローの理解の仕方はちょっと特殊で、「その世界にいて相互関係できるような存在」としてとらえている。ただそこにたぶんもう1個特殊な理解の仕方が混ざってる気がしますね。中の人たちは、読み物としてもスーパーヒーロー概念を理解しているんです。フラッシュの場合はそのへんが変なぐあいになっている。別の世界に行ったフラッシュは「俺が読んでいたあの人がいる」のようなことを言っていて、そのへんが混乱していて面白いですね。
参加者B
「虚構内的な虚構外的概念」みたいな。
高田
マンガの中にマンガが出てくる場合はそうなりますね。
岩切
ユニバースとかだとニューヨークの人は隣人としてスーパーヒーローを知っているということで、コミックを通して知るわけではないということですか。
高田
マーベル・ユニバースにマーベル・コミックはあるのかというのは今一つ一貫していなくて、あるようにも見える。マンガ読んでるときもあるんだけど、実話が描かれたマンガが売っているのかどうかはよくわからない。
森
〔実話だったら〕フィクションじゃなくてレポートになっちゃう。
参加者B
スーパーヒーローが活躍していることを虚構内の人々が知る場合にはどうやって知るんですか。
森
ニュースですよね。「バットマンが現れました」みたいなのがニュースに出るでしょ。
高田
作中でノンフィクションとしてスーパーヒーローコミックスが売っているみたいな描写があるときもあります。そこは今一つ一貫はしていないんですけど。
参加者D
描いている人は年代によって全然違う人だからつじつまが合わないことも出てくるでしょうね。
高田
そうですね。
ハッキング的な手法の「分析哲学」や「分析美学」という哲学カテゴリーへの適用可能性
参加者E
高田さんの今回の概念史のハッキング的な手法というのは、フィクションのカテゴリーとかジャンルの変遷を追う際に有効じゃないかというお話だったと思います。分析哲学・分析美学という哲学のカテゴリーの変遷に関してもこれは使えるんじゃないかとも思うのですが、分析哲学の概念史のようなものをやるおつもりはないのでしょうか。
高田
面白いとは思うんですが、大変ですよね。笠木〔雅史〕さんのやっていることはそれに近いですね。分析哲学という言葉の意味はだいぶ変わっているという話はよくされています。
参加者E
ちなみに「分析美学」という言葉の初出はいつなのでしょう。
岩切
1950年代では今分析美学の主流の雑誌では全然分析美学はやっていない。むしろ、Journal of PhilosophyとかMonistとかで分析哲学者が美学について論じている。分析美学をやっています、というような人はいなかったと僕は思ってます。
森
アメリカ美学会は昔はもっと雑多な学会だったのだが、徐々に哲学者に侵食されていって最近は分析美学者っぽい人しかいなくて、それはむしろよくないと言われている。
参加者D
ハッキング的な手法の応用例としては『概念分析の社会学』がありますよね。哲学というジャンルへの応用としては、ハッキング自身の『言語はなぜ哲学の問題になるのか』。
次ページ「岩切氏への質問と応答」へ続く