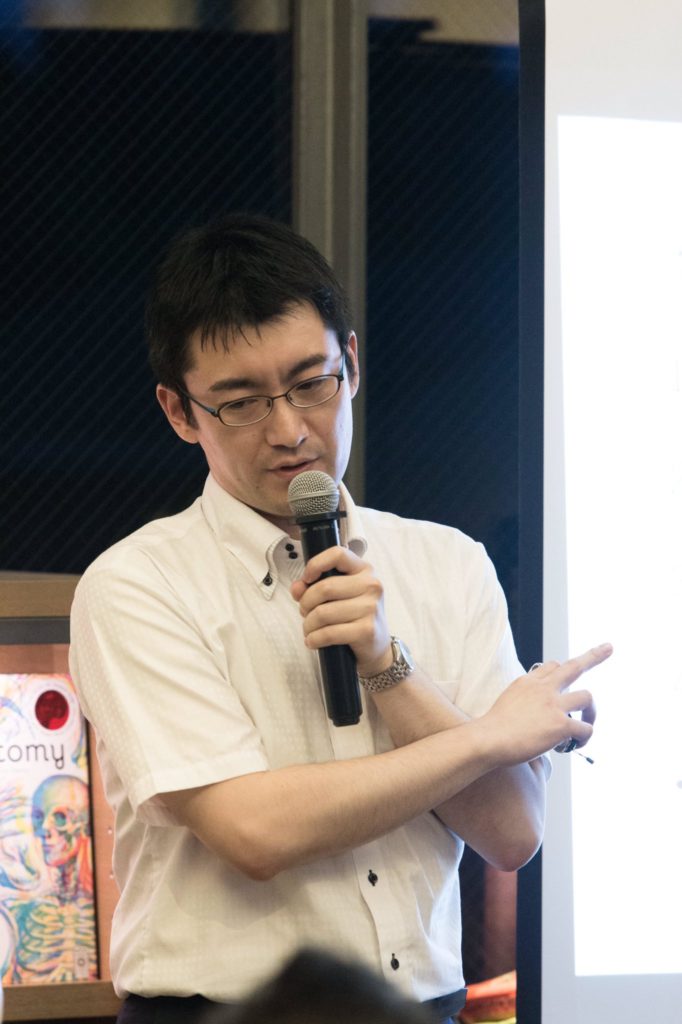去る6月26日、代官山蔦谷書店にて、弊誌主催トークイベント「ネタバレのデザイン」が開催されました。これは、フィルカル最新号での特集「ネタバレの美学」にちなんだもので、そこでの議論をより発展させたものです。登壇者は分析美学から森功次氏と松本大輝氏、そして現代思想に造詣の深い批評家の仲山ひふみ氏のお三方です。この記事では、大変盛り上がった当日の様子を報告したいと思います。
まず企画者である森さんが全体的な説明をしてくれました。森さんは、これまでのイベントや雑誌特集でネタバレについて論じ切れた、あるいは論じきろうとはまったく思っていない、と強調されました。森さんは、ここまでの活動を美学においてネタバレという新しいテーマを作り出すための運動と考えており、今後はさらにネタバレについての歴史学的、社会学的なアプローチも各分野の研究者と協力して展開していきたい、と展望を述べられました。
ではそもそもなぜネタバレを論じようと思ったのか。世の中にはネタバレがよくないことだと考える人と、問題ない、むしろよい(より豊かな鑑賞ができる、感情を揺さぶられすぎずに落ち着いて鑑賞できるetc.)という人がいて、どちらもそれなりに根拠をもった説得力のある主張をしているように思える。そのうえ、こうした二つの考えが対立することも明らかで、ときには暴力事件を引き起こしたりもしている。にもかかわらずこの対立を解消、もしくは理解するための分析は行われていない。こうした状況が基本的な背景にあります。
そのうえで、少しネタバレについて哲学者が考えてみると、「ネタバレ」という言葉で意味されているものには、実際にはかなり異なるものが複数含まれていて(ネタバレ情報、ネタバレ行為、ネタバレ接触など)、多くの人が曖昧なままひとつの語を使うことで基本的に混乱した状況になっていることがわかる。こうした状況を見るとひとつ用語の整理をしたくなるのが哲学者の性というものだ、と森さんは言います。用語整理を行ってから問いを定式化し、その問いに答えようとする、というのは分析哲学の典型的な方法論ですが、確かにネタバレはまさにこうしたやりかたがぴったり当てはまる、分析美学にとってうってつけの題材と言えるのではないでしょうか。
松本さんの発表が森さんのフィルカル4-2号掲載論文への批判なので、ここで森さんはこの論文の内容をコンパクトに紹介しつつ、ネタバレをめぐるこれまでの議論を簡単にまとめます。結論としては、自分からネタバレ情報を見ることは、美的に悪いのは当たり前であるだけでなく、倫理的にも悪い、というのが森さんの主張です。理由となるのはおもに、作者への敬意を欠く、アートワールドの腐敗を招く(芸術作品やその鑑賞を可能としている文化や社会そのものを破壊する行為である)、の二点です。もうひとつ森さんがこの論文で言いたかったのは、犯人や結末の情報だけでなく、事前に作品についてのなんらかの情報を得ていることで、清新な感動が薄れるということがかなりある、したがってネタバレにあたるものを、あえてもっと広くとったほうがいいのではないか、ということです。ここで例に挙げられていたのは、展覧会の前にその展覧会のパンフレットを見る、という『美味しんぼ』で取り上げられている事例でした。最後に、ネタバレ許容派の言い分への批判も具体的にこの論文では述べられています。ネタバレ許容派のいうことは基本的には何度も繰り返し見たくないから、という鑑賞効率を優先としたものであって、効率を優先するということが作品を鑑賞する場の価値観とは別の領域の価値観に従っている、というのが森さんの大筋の議論です。効率という別種の価値を優先しているのに、〈より良く楽しめる〉といった芸術性を擁護するかのような弁明をしているのは欺瞞だ、と森さんは考えます。
ここで松本さんにバトンタッチ。松本さんによる森さんの論文への批判は、自発的にネタバレ情報を見に行くことは悪ではない、少なくとも擁護できるタイプのものがある、というものです。その根拠となるのは二点、森さんは自発的なネタバレ接触をする人は、ネタバレ情報によって一回で効率的に作品を理解しようとするのではなく複数回見るべきであると主張していますが、この主張は森さん自身の議論と不整合であるということと、ネタバレ接触はアートワールドを必ずしも腐敗させるとは言えず、むしろネタバレ接触によってしか達成できない望ましい鑑賞がある、というものです。
まず松本さんは、ネタバレ接触を本質的なものと非本質的なものに分けます。なにが本質的なものになるかは作品によって異なりますが、たとえば推理小説を読んで、犯人が明確に説明されているにもかかわらず、誰だかわからなかったという人がいたら、その人は「その小説を読んだ」とは言えない、と言えるでしょう。そうした情報、この場合は誰が犯人であるかという情報を事前に知ることは本質的なネタバレ接触です。それに対して、ある映画の1シーンが別の作品のオマージュになっていることに気づかなかったからといって、その映画を見たことにならない、とは言えないという場合がありえます。このとき、このオマージュについて事前に知ることは、非本質的なネタバレ接触である、というわけです。森さんの議論は、積極的にネタバレを広く取ることによって、非本質的なネタバレ接触をも攻撃の対象としており、松本さんはそこに異議を唱えたいわけです。
ネタバレ擁護派には、批評などを読んでから鑑賞することでより豊かな鑑賞ができるようになる、と主張する人がいます。確かに鑑賞をよりよいものにするのは、作品批評の重要な役割でしょう。これに対し森さんは論文中で、それなら初回は批評を読まずに見て、初回鑑賞時の驚きをきっちり経験し、それから批評を読んで、面倒がらずに二度目以降の鑑賞をすればよい、と批判しています。松本さんはこの点をついて、森さんはネタバレが初回鑑賞では許されず、二度目以降では許されるという、初回鑑賞の特権性を前提している、と言います。ここで、二度目以降で許されるとされるネタバレは、非本質的ネタバレであることになります。というのも、本質的ネタバレになるような情報は定義上、初回鑑賞で見逃されないことを前提とするような情報だからです。したがって森さんは、非本質的ネタバレ接触に関しては、二度目の鑑賞以降許される、と考えていることになります。しかしこれは森さん自身の立場では許されない帰結ではないでしょうか。
松本さんによれば、このツッコミに対する森さんの取りうる態度は二つあります。ひとつは、悪とされるネタバレ接触の種類を本質的ネタバレ接触のみに縮小する、というものです。これはネタバレの概念を広げたいという動機を断念することになるので、森さんにとって些細な修正とは言えないと思いますが、松本さんはこの路線を取るなら、特にこれ以上批判する点はないと言います。もう一つは、初回鑑賞特権を捨てて、二回目以降の非本質的ネタバレに関してもこれを悪とみなす、というものです。この場合、いくら鑑賞回数を重ねても作品に含められた情報をすべて把握できるとは限らないので、批評を読めば可能になったであろうより豊かな鑑賞経験が禁じられてしまう可能性があります。すると森さんは、初回で読み取れる情報のネタバレとそうでない情報のネタバレという区分を受け入れる限り、ネタバレ擁護派が必ずしも効率重視ではなく、豊かな鑑賞経験のために擁護している可能性を見落としているとは言えないでしょうか。
初回鑑賞特権という考え方は、森さんに限らず、広く受け入れられているようにも思えます。それは我々の芸術作品をめぐる実践を規定するアートワールドが、初回鑑賞特権を受け入れているということです。ですがこのことは、ネタバレはアートワールドを腐敗させるという森さんの用いるもうひとつの論拠を突き崩す可能性がある、と松本さんは言います。もしアートワールドが初回鑑賞特権を認めるなら、それはアートワールド自体が非本質的なネタバレ接触、二回目以降の鑑賞におけるネタバレ接触を肯定していることになります。そして、アートワールドがこうしたネタバレを容認しているということは、発見の楽しみという芸術的価値と、より豊かな鑑賞という芸術的価値のあいだの「取引」を肯定しているということです。そうであるなら、ネタバレを通して、批評活動などによる「分業」によって、どの芸術的価値をどのように配分した鑑賞がもっとも理想的であるのかを追求する場をアートワールド自体が構成しているとすら主張できる可能性があります。以上が松本さんの発表の骨子でした。非常に重厚な内容ですが、明解で、あっと言わせる指摘の数々に、聞いていて何度も息を飲むような瞬間がありました。
続いて三人目の登壇者、仲山さんです。仲山さんは森さん、松本さんのような分析美学の研究者ではなく、批評家としてという自らの立ち位置にこだわり、ネタバレを論じるというこの場の営みそのものをメタ的に論じる、ということを念頭においていると初めに話されました。仲山さんによれば、分析哲学(美学)は、人文系の学問の中でも特に議論の作法が明確に定まっており、限られた時間やリソースをなるべく無駄にしないような、緻密な議論を作るために学問全体が構成されています。このように組織化されていることを、仲山さんは「アーギュメント」がある、と表現するのですが、フランス現代思想がアーギュメントを積極的に排除していった結果、理論としてでなく、実践や政治思想としてしか顧みられなくなってしまった、それに対する反省として、思弁的実在論のような、フランス現代思想を継承しつつもアーギュメントをもった思想が現在生まれつつある。そのようなアーギュメントの復権という流れのなかに、仲山さんは分析哲学も位置づけられると考えているようです。
仲山さんが今回のトークで目指されたのは、ネタバレ概念を極限まで一般化する、というものです。まず、ネタバレを論じることは情報を論じることのうちに含まれるわけですが、情報がすなわち権力と捉えられる文脈が存在することを、原爆の開発状況をめぐる大国間の情報戦についての柄谷行人の発言、サイバネティクスを西洋形而上学の完成とみなしたハイデガー、さらにはアインシュタインの一般相対性理論などを引きつつ、力、情報として一元論的に世界をのものが捉えられるようになった、というスケールの大きい話によって示されました。
ネタバレを一般化する二つ目の観点が、資本としての情報、というものです。知的財産権自体の原型はすでに15世紀のイタリアに見られますが、1990年代以降、情報は資源という概念の中核に位置するようになりました。こうした情報のやりとりから生まれる認知労働の主体が、ネグリとハートがその主著である『帝国』でマルチチュードと呼んだものです。現在の資本主義は、いわばネタバレされてはいけないものとしての情報を中心に成立しています。また、四、五年前に、シェア経済、限界費用ゼロ社会ということが盛んに論じられたことがありました。これはYouTubeのようなサイトが典型的なのですが、音楽を無料でシェアするなど、デジタル化によってコストをかけることなく作品の情報が共有される社会のことなのですが、こういった社会は一般化されたネタバレ行為を前提としたユートピア、と表現することもできます。また、ネタバレについての論争が生じてきたタイミングと、作品の情報を共有することによる二次創作的な空間の可視化は同時に起こってきたようにも思えます。この二つの動きは、我々の社会における作品概念の変容と軌を一にしているのではないでしょうか。
最後に、享楽という観点からネタバレを捉えることができます。ここでいう享楽とは、ジャック・ラカンに慣れ親しんでいる人にはわかりやすいものですが、快楽と対になる概念で、ネガティブな振る舞いによってもたらされるような快のことです。この場合では、作者の意図した仕掛けにのっとって作品を鑑賞する楽しみを快楽とするなら、ネタバレを禁じたり、あるいはそうした禁止にしたがうことで感じるのが享楽だといえます。最近では『カメラを止めるな』で、制作者側がすでに鑑賞した観客にネタバレしないようにと積極的に働きかけたということがありました。このとき観客側が実際にネタバレしないことで、ある種の伝言ゲームの楽しさを共有するという現象が見られました。このように、ネタバレされる側が保証されるべきであった、ネタバレから守られるべき快楽だけでなく、ネタバレをする側、あるいはネタバレを我慢する側の快楽や享楽といったものも同時に論じることで、ネタバレというものをより広い観点から論じることができるのではないでしょうか。このように分析哲学とは異なるやり方でネタバレを論じる仲山さんの発表は、一気に視界を広げるような刺激と興奮を会場にもたらしていました。
ここからは、登壇者と会場のみなさんが入り混じっての議論になりました。会場からの質問に登壇者が答え、それにまた別の登壇者が疑問を挟み、呼応したかたちで会場からまた別の質問があがり、というふうにテーマが自然と収束し、ライブなやりとりのなかで共同作業のように議論や分析がどんどん進んでいく様子が大変面白かったです。
そうして会場でできあがっていったテーマのひとつが、ネタバレの「ネタ」とはなにか、という問題でした。これも最初に会場からの質問というかたちで始まった議論ですが、ここでいうネタとは、いわゆる命題的な、言語的に表現されうるような情報である必要はない、たとえば映画の予告編において、実際の作品とまったく同じものが部分的に経験される場合、ここで経験されているものは必ずしも命題によって表象可能ではないかもしれないが、それもネタバレになる。また、ネタバレを問題にすることは、作品そのものを情報としてみているということでもない。たとえば、このボタンを押すとこの作品に含まれている情報がすべて得られます、と言われても多くの人は押さずに作品自体を鑑賞しようとするだろう、人は情報を得るために作品を鑑賞するのではなく、作品を味わうために鑑賞するのである。ネタバレにおいてはあくまで、情報を得ることによって鑑賞という経験が損なわれることが問題なのであって、情報を得ることそれ自体は作品鑑賞の主眼ではない、といった感じに議論が進行していきます。また、宗教画を鑑賞する際にはそこで描かれている聖書のエピソードを知っていることはネタバレになるのか、あるいは逆に知っているほうがよりよい鑑賞を可能になるのか、という質問も寄せられ、それはたとえば現代と中世では異なってくる、したがってなにがネタバレになるのかというのは、同一作品であっても、時代や文脈によって異なる、あるいは個々の鑑賞者ごとに異なるものでありうる、という議論がそこから生まれ、トーク中には直接論じられることのなかったネタとは何か、ということが目の前で次々分析され、明確化され、思いもよらぬ展開を見せていました。
このように会場全体の共同作業として哲学がいわば生まれていくその瞬間を目の当たりにし、自分もそこへ参加するという楽しみは、こうしたイベントならではのものだと思います。フィルカルでは今後も様々なテーマでイベントを企画しています。専門的な知識などは特に必要としませんので、ほかではなかなか味わえない知的作業の興奮をぜひ会場で直接経験してみてください。
フィルカル編集部 佐藤 暁
イベントの元となった特集「ネタバレの美学」は、最新号でお読みいただけます。
Amazon でご購入いただけます。